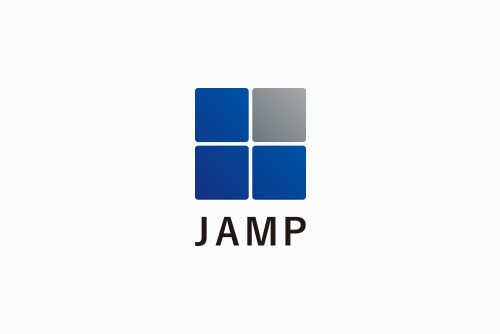2022.08.31インタビュー
対談連載【金融ビジネス/これからの「顧客本位の業務運営」 No.14】日本証券アナリスト協会認定アナリスト 元・日本証券経済研究所特任リサーチ・フェロー 杉田浩治氏「日本の投資信託を60年間見てきた私から言えること」
杉田浩治氏(日本証券アナリスト協会認定アナリスト 元・日本証券経済研究所特任リサーチ・フェロー)
聞き手:長澤敏夫(株式会社日本資産運用基盤グループ 主任研究員)

今回、お話を伺った杉田浩治さんは1961年、野村アセットマネジメント(当時は野村證券投資信託委託)に新卒入社し、企画部長やニューヨーク駐在員事務所長を歴任。2003年に定年退職された後も、投資信託協会の参事、主任研究員、日本証券経済研究所の専門調査員、特任リサーチ・フェローなどで国内外の投資信託の研究を行ってきました。国内外の投資信託制度の違い、日米の投資信託市場規模に、なぜこれだけの差がついてしまったのか、などについてお話を伺いました。
投資信託一筋のキャリア
長澤 まず、杉田さんのご経歴からお話下さい。
杉田 1961年に野村證券投資信託委託に新卒で入社しました。現在の野村アセットマネジメントです。以来、60歳の定年退職を迎えるまで、ずっと投資信託一筋です。1995年には、野村證券投資信託委託が1990年に創業30年周年事業の目玉として設立した「日本投資信託制度研究所」に出向となり、資産運用ビジネスの専門研究誌である「ファンドマネジメント」の編集長を経験させてもらいました。
2003年に定年退職してからは3年間、投資信託協会の参事、2014年から2018年まで投資信託協会の主任研究員であったのと同時に、2006年から2018年まで日本証券経済研究所の専門調査員、特任リサーチ・フェローの職にありました。
長澤 杉田さんの人生そのものが日本の投資信託の歴史と言っても過言ではないと思うのですが、野村アセットマネジメントでのキャリアのなかで印象的だったことはありますか。
杉田 企画畑が長く、20数年間をそこで過ごしたのですが、関わった案件で印象的だったのは、まず日本のMMFの前身ともいえる「中期国債ファンド」の設立ですね。1978年に米国の現地調査を行ったのですが、当時は米国の銀行にも金利規制があって、預金利率は上限が設けられていました。そのなかでMMFは金利規制の対象外で、しかも1978年から市場金利が上昇したこともあり、銀行預金の利率よりも有利な運用成績を出していたMMFに対する注目度が高まり、銀行預金からMMFに資金が大量にシフトしたのです。
それを日本の銀行も警戒しており、なかなか米国のMMFと同じスキームの商品としては認めてもらえなかったため、中期国債の円滑な消化を大義名分として、中期国債ファンドを認めてもらいました。
また、今では当たり前ですが、投資信託会社が投資顧問業務を兼業できるようにしたことや、野村投信が設定・運用するファンドを、野村證券以外の全国の証券会社に販売してもらう「公開販売ファンド」などもスタートさせました。

日米の投資信託市場に格差が生じた理由
長澤 杉田さんは1987年末から3年ほどニューヨーク駐在員事務所長を務めておられました。米国から見た当時の日本の投資信託業界について、どのような印象を持っていましたか。
杉田 当時、日本はバブルの絶頂期だったので、今では信じられないかも知れませんが、野村投信は世界最大の投信運用会社でした。ちなみに89年末時点で、野村投信の運用資産残高は16兆円だったのですが、米国で最大の投信運用会社だったフィデリティが14兆円でしたからね。
国ベースで見ても、投資信託の残高は米国が9800億ドル、日本が4000億ドル、欧州は全体で5000億ドルという状況でした。日本は米国に次ぐ投資信託大国だったのです。ですから、米国の投信業界関係者から、「日本ではどうなっているんだ?」というように、日本の状況を聞かれることも結構ありました。
それが今では、米国の投資信託が大発展を遂げて、2021年末で見ると日本の公募投信残高は、米国のそれに比べて24分の1になってしまいました。
長澤 なぜ、これだけの差が付いてしまったのでしょうか。
杉田 株式・債券・為替の市況要因(たとえば、株価は米国のS&P500指数が89年末から21年末にかけて13.5倍に値上がりしたのに対し、日本のTOPIXは0.7倍に値下がりしたこと)が一番大きかったと思いますが、その他に制度・販売の問題もあります。
米国では1970年代に、経営学者であるドラッカーが、確定給付型(DB)企業年金が急成長するなかで、「見えざる革命」という本を書いたのですが、そのなかで「年金基金が米国経済の資本を支配する」という指摘がありました。
ところがその後、米国においては徐々に企業年金が確定拠出型(DC)に移行し、年金資金運用の個人化が進むにつれて投資信託の市場が大きく拡大していきました。今では「投信資本主義」ともいうべき様相を呈していると言っても良いでしょう。
FRBの資金循環統計で株式の保有者別構成を調べると、2021年末現在でETFを含む投資信託が27%を占め、私的年金基金の5%をはるかに凌駕しています。
それは、投資信託が米国の家計における株式保有比率の上昇に、大きく貢献したことを意味します。FRBの調査によると、2019年現在で米国全世帯のうち、上場株式を保有する世帯は53%に達し、30年前の1989年当時の32%から大きく上昇しました。そのなかで、株式を直接保有している世帯の比率は、30年前の17%から15%に減少する一方、投資信託や退職準備口座を通じて株式を間接的に保有している世帯の比率は、15%から38%へと増加しました。
つまり米国では長い年月を費やして、投資信託による資産形成が家計に定着するような制度・販売体制を構築していったところに、これだけ大きく成長した原因のひとつがあるように思えます。

販売体制や制度の問題
長澤 販売体制の違いとは、具体的にどういうことが考えられますか。
杉田 まず商品についてですが、日本の場合、数年前までは新ファンドの販売に偏っていた面があることは否定できません。
米国の場合、新ファンドが人気化することは、まずありません。なぜなら過去の運用実績がないからです。最低でも3年、あるいは5年程度の運用実績をチェックしたうえでファンドを選ぶのが普通です。逆に言えば、過去の運用実績がない新ファンドは売れません。
これは販売チャネルの関係もあります。米国ではIFAを含む、独立性の高いファイナンシャルアドバイザーを経由して投資信託を購入することが多いです。しかも大半のファイナンシャルアドバイザーは、地域密着型です。自分が事務所を構えている地域のお客様を対象にして投資信託を販売していますから、不適切なファンドを販売してクレームなどを受けると、今後そこで商売が出来なくなる恐れがあります。つまり自分の身を守ると言う意味でも、長期の実績を持つファンドを勧めているのです。
あとファイナンシャルアドバイザーの報酬体系の問題もあります。今は販売手数料ではなく、残高報酬がメインになっていて、手数料稼ぎを目的にした乗り換え営業が行われにくい環境になりつつあります。もっと言うと、残高報酬もファンドの信託報酬という形で受け取るのではなく、お客様から直接、その預かり資産残高に応じたフィーを受け取る形に移行しつつあり、信託報酬率の高いファンドを積極的に販売するといったバイアスがかかりにくくなっています。
それ以外には、米国の個人が投資信託を購入する目的は、圧倒的に退職後の資産形成であるのに対し、日本はどうかというと、単に「儲けたい」という考えで投資信託を買うケースが少なくありませんでした。結果的に日本の投資信託は、目先儲かりそうなテーマを掲げたものが中心になり、購入する個人も、短期的な利益追求を目的にした買い方になりがちだったのです
長澤 分配制度や税制の違いが、日米の投資信託市場の成長度合いの差につながった面はありませんか。
杉田 まず日本の投資信託の分配規制は、米国のそれに比べて格段に緩やかです。
分配金の原資はインカムゲインとキャピタルゲインの2つで、このうちキャピタルゲインは実現益と含み益の2つがあります。かつては日本も実現益しか分配原資にできなかったのですが、1960年代に分配金競争が激化した時、一部の投信運用会社が含み益を持っている銘柄を決算日直前に売却して実現益を確保し、再び同じ銘柄を同数買い付けるといった取引をすることがあったようです。
ただ、これではいたずらに組入銘柄の売買コストを引き上げることになるので、評価益も分配原資とすることが認められました。そして分配原資のどこまでを分配するかについては、投信運用会社各社の判断に委ねられています。毎月分配型投信は、この制度を上手く利用したものと言えるでしょう。
もちろん、分配が悪いなどとは言うつもりはないのですが、米国の場合は高齢者よりも働き盛り世代の投信保有率が高く、その世代は自分の老後に備えるために投資信託を購入しますから、分配金の9割以上が再投資に回されています。そのため残高が大きくなりやすい面はあるでしょう。日本のように再投資率の低い分配をすれば資金が流出するので、残高が増えにくくなります。
また税制については、米国の確定拠出年金は税の優遇度が非常に大きなものになっています。2022年現在、企業型では年間拠出限度額が企業・個人を合わせて6万1000ドルです。仮に1ドル=130円で計算すると793万円です。個人拠出分だけでも2万500ドルですから266万円相当が、税の優遇措置を受けながら投資できるのです。しかも、50歳以上には6500ドルの追加拠出も認められています。
さらに言えば、米国株の長期リターンが高く、米国人の間で株式投資に対する信頼度が高いことも、投資信託の市場規模が大きくなった背景にあると思います。その点では日本も、日本株の長期リターンを高めるような努力が必要でしょう。

日本の投資信託を取り巻く環境は改善された
長澤 日本の投資信託市場が成長していくうえで検討するべき課題は何でしょうか。
杉田 まず、日本の投信運用会社の主戦場となる国内株ファンドについてですが、最近のパフォーマンスはインデックスを上回っていて好調です。
野村総合研究所の投信評価レポートによると、日本籍国内株式ファンド全体の2021年末までの5年間累積リターンは、53.8%に達しており、配当込みTOPIXの46.9%を上回りました。
運用成績の向上は、投信運用会社にとって永遠の課題といっても良いでしょう。その達成に向けて運用手法の高度化を図るのはもちろん大事ですが、主要投資対象である日本企業の価値向上を実現するために、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードという2つのコードの履行・拡充を進める必要があります。
また、投資リターンを向上させるという点では、プライベートエクイティのようなオルタナティブ投資も検討するべきでしょう。
第二は販売改革です。長期投資を促進するという観点から、投資信託販売のビジネスモデルを販売手数料依存型から残高報酬重視型に切り替えていくことが望まれます。残高報酬型にすれば、販売業者とお客様の利益が合致します。そして、優遇税制が適用される確定拠出年金、NISAを活用して、「長期・積立・分散投資」を徹底的に推進し、特に今まで投信保有率が低かった若年層の投資への参加を促進する必要があります。
第三は商品政策です。新商品重視ではなく、既存商品を大事に育てていく姿勢を強めるべきです。国際分散投資の拡充も重要で、そのために運用の外部委託を行うこと自体は何も問題はないのですが、日本の投信運用会社としては、せめてアジア市場についての運用ノウハウを高めることに期待したいところです。
最後に、これは中長期的課題といっても良いと思いますが、米国で大きく伸びているETFを、日本の投信ビジネスにどう取り込んでいくかを詰めておく必要があります。ETFは現物株式の拠出・引き出し型なので、ポートフォリオの組成や取り崩しの際のコストが安く済みます。こうした利点を活かして、ETFを含めて投資信託市場全体の拡充につなげたいところです。

長澤 最後に、投資信託の組成・販売の現場で頑張っている金融機関の役職員の皆さまにメッセージをいただけますか。
杉田 第一に、合理的で透明性の高い投資信託という金融商品に自信をもっていただきたいと思います。合理性と透明性は、投資信託という仕組みの特徴といっても良いでしょう。
投資信託は共同投資により分散投資と専門家運用を可能にするという合理的な仕組みに基づいて運営されており、世界中で成長しています。今や投資信託は、国際投資信託協会加盟国だけでも46カ国で運営され、その資産規模は2021年末現在、公募分だけで65.2兆ドル、7500兆円規模に達しています。
また日々、組入資産を時価評価して基準価額を公表している他、目論見書による詳しい商品説明、運用報告書による詳細な運用状況説明、さらに投信運用会社のホームページで月次の運用内容が開示されています。金融商品のなかでは最も透明性が高いといっても良いでしょう。
第二に、投資信託の販売環境は10年前、あるいは20年前に比べて格段に良くなっています。たとえば確定拠出年金やNISAといった制度は、2000年当時にはありませんでした。ファンドのコストは大幅に下がり、世界分散投資を低コストで行うことができますし、投資家心理を悪くしていた日本の株価低迷も、10年ほど前から好転しています。2021年末までの10年間のTOPIX上昇率は174%に達し、米国の279%には及びませんが、ドイツの169%、フランスの126%、イギリスの33%を上回っています。
また日本経済は、長期のデフレからインフレへと転換する気配を見せており、インフレに強い資産として株式組入商品が注目されやすい環境に変わりつつありますし、個人の間でも若年層や中年層が資産形成への関心を高めつつあります。
こうした環境変化も生かして、是非とも日本人の資産所得を増やすべく日々の仕事に邁進していただければと思います。
長澤 ありがとうございました。
(*)日本資産運用基盤の対談連載【金融ビジネス/これからの「顧客本位の業務運営」】の全てのバックナンバーはこちらからお読み頂けます。