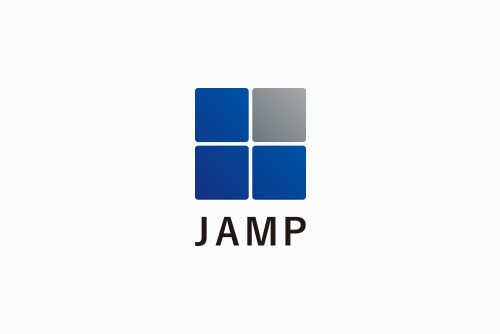2023.04.25インタビュー
【金融ビジネス:対談連載】これからの「顧客本位の業務運営」 No.18 社会人になった時に思った「顧客本位の気持ち」を持ち続けることが大事
清家武氏(株式会社QUICK資産運用研究所所長)
聞き手:長澤敏夫(株式会社日本資産運用基盤グループ 主任研究員)

銀行が投資信託の窓販を開始して25年近くが経ちました。日本版金融ビッグバンの一環として行われた投資信託の販売チャネルや商品性の多様化が進むなか、販売金融機関はどのようにして「顧客本位の業務運営」を構築してきたのか。株式会社QUICK資産運用研究所所長の清家武さんに話を伺いました。
まずは現場に出向く
長澤 まず経歴から教えて下さい。
清家 山一證券に入社して、個人や法人を相手にした営業を主に担当していました。正直なところ、当時は「顧客本位の業務運営」というにはほど遠いような会社の収益を優先した営業をしていたのですが、だからこそ今、顧客本位の業務運営の重要性をしっかりと認識して、それを多くの人たちに伝えるという仕事に従事できていると考えています。
1997年に、山一證券が自主廃業した後、日経グループのQUICKに入社しました。そして、投信評価会社のQBR(QUICK Business Research)に出向し、投資信託の分析や、投資信託ならびに資産運用に関わるサービスの企画に従事し、日本経済新聞などに記事を書いたり、テレビやセミナーで、投資信託や資産運用に関する情報を発信したりしてきました。
その後、QBRからQUICKに戻り、QUICK資産運用研究所に所属し、個人投資家や証券会社、銀行などの営業担当者に役立つ情報やツールを提供する仕事をしています。
QUICK資産運用研究所は非常に幅ひろい人材が在籍しているのも特徴です。銀行、証券会社、運用会社の出身以外にも、元金融メディアの記者、それ以外にもクオンツアナリスト経験者、大学教授経験者もいます。そのように、幅広い人材を集めて、顧客本位のビジネスを展開しています。
長澤 現在の業務で大事にしていることは何ですか。
清家 やはり現場に出向くことですね。記事を書いたり、テレビで解説したりしていますが、机上論ではなく、まずは現場に行くことを心がけています。証券会社、銀行、運用会社などの金融関係者、金融庁などの監督官庁、メディア関係者など、この15~20年は年間延べ200社の人たちと面会しています。3000人以上の業界の方と面会しているかもしれません。最近はオンラインで取材する人も増えているようですが、実際に現場で直接会って話を聞くと、新聞などのメディアで語られていることとは違う話を聞くことができます。いささかアナログではありますが、本当に大事な情報はインターネットに出ていないことが多いので、丹念に足で稼ぐことが大事だと思います。
これは山一證券時代の営業で身に付いた癖なのかも知れませんね。営業の仕事も、一人でも多くのお客様と直接、会うことによって、お客様の気持ちが分かるようになるし、電話では分からないお客様の情報を入手することができます。
要領よく器用な人が身に着けたような知識は、廃れるのも早いものです。不器用でも、きっちりひとつひとつ、汗をかいて身に着けたものは、確実に身に付きます。短絡的な視点でつくるのではなく、本当に良いものをつくるのが大事ですし、枝葉の情報はインターネットで検索できますが、本質的なことが何も見えてきません。特ダネ情報を掴むよりも、本質を見極めることに重点を置いています。

顧客本位の業務運営に必要なこと
長澤 顧客本位の業務運営について、思うところをお聞かせいただけますか。
清家 山一證券の自主廃業は、私の「顧客本位の業務運営」に対する考え方に大きな影響を与えたと思います。
この春も、茅場町などを歩いていると、大勢の新入社員を見かけますが、その中の1人たりとも、不祥事につながることをしようなどとは思っていませんし、お客様のことを考えて仕事をしようと思っています。
でも、仕事を始めて数字に追われるようになると、いつの間にかこの大事な気持ちが失われていきます。自らの収益を最優先させて、何か失敗をすると嘘をつくようになり、それが重なって取り繕うようになります。その蓄積が不祥事になっていくのです。
そうならないようにするためには、企業も社員も強い信念、理念を持ち続けることが大事であり、またそうしないと「顧客本位の業務運営」を継続するのは難しいと思います。
私は、自分で起業して資産を築いた経営者にも大勢インタビューを行っていますが、共通する点は、お金持ちになることを目的にして、今の財産を築いたのではないということです。やはり多くの人に喜んでもらいたい、そして社会のためになりたいという一心で良い製品・サービスを生み出した結果、お金は後からついてくるものなのです。それが本当の仕事なのではないか、と思います。

銀行による投信窓販の歴史
長澤 ところで清家さんは、銀行の投信窓販をご自身の目で見ていらっしゃいます。当時、どういう状況だったのですか。
清家 バブル経済の1980年代まで、日本の銀行は護送船団方式といって、体力の弱い銀行に合わせるようにして預金金利やサービスを規制し、弱い銀行を保護する政策を取っていました。それが日本の金融市場の自由化を進めるために行われた金融ビッグバンによって、金融業界にも競争原理が導入されました。
そのなかで、バブル経済崩壊の影響による不良債権問題などを背景にして、多くの金融機関が経営破綻に陥りました。1997年の山一證券、三洋証券、北海道拓殖銀行に加え、1998年には日本長期信用銀行、日本債券信用銀行が破綻したのです。銀行の投信窓販がスタートしたのは、まさにその金融不安の渦中にあった1998年のことでした。
かつて投資信託は証券会社でしか買えなかったのですが、銀行の投信窓販が解禁されたことによって、銀行でも買えるようになりました。
また、山一證券や三洋証券など証券会社の経営破綻や廃業が増えたことで、大勢の証券会社の人材が銀行に流れました。これによって、銀行の投信窓販の体制がいち早く構築されたという側面があったのも事実です。
さらに、証券会社の人材は運用会社にも流入し、銀行向け研修などのサポート体制が強化されました。
こうして早期のうちに銀行の投信窓販は体制を確立し、実際大きく成長しました。ETFを除く追加型投資信託の純資産残高は、1998年当時は10兆円程度でしたが、約8年後の2007年には50兆円近くまで膨らみ、さらに2008年には純資産残高で銀行が証券会社を抜き、投資信託の販売チャネルとして無視できない存在になりました。
一世を風靡した投資信託
長澤 この間、どのような投資信託が人気を集めていたのですか。
清家 「グローバル・ソブリン・オープン」や「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」などの毎月分配型ファンドの他、「財産3分法ファンド」、「マイストーリー分配型」、「GW7つの卵」など、複数の資産クラスに分散投資するバランス型ファンドが人気を集めていました。
2007年くらいまではその人気が続いたのですが、2008年にリーマンショックが起こり、ほとんどの資産が大暴落しました。当初、バランス型ファンドは分散が効いているので、比較的安定しているという触れ込みでしたが、すべての資産クラスが暴落してしまったため、バランス型ファンドの運用成績も急落してしまい、資金流出が拡大しました。
特に銀行で投資信託を購入していたお客様にとっては、初めての大暴落でしたから、その対応が懸念されましたが、何とかアフターフォローも含めて対応はできました。
長澤 リーマンショックの後、相場の回復局面ではどのような投資信託に人気が集まったのですか。
清家 この時に台頭してきたのが「通貨選択型ファンド」でした。2009年に「野村米国ハイ・イールド債券投信」がヒットして、通貨選択型ファンドが大量に設定されるようになったのです。
相場回復局面では、値動きの大きな投資信託の方が鋭角的に値上がりするということもあって人気を集めたのですが、ハイリスク・ハイリターンということもあり、大きく損をするファンドもありました。
正直、通貨選択型ファンドは為替ヘッジやデリバティブを多用した商品設計になっていたため、お客様はもちろんのこと、商品を販売していた販売担当者も、本当の意味で中身を理解している人は、ほとんどいなかったのではないかと思われます。
その他、2013年以降は米国の景気回復が顕著となり、米国REIT、米国ハイ・イールド債券など米国の資産を対象にしたファンドが人気化しましたし、2016年くらいになると、人気が米国REIT型に一極集中するようになり、高分配を売りにした「フィデリティ・USリート・ファンド」や「新光US-REITオープン(ゼウス)」などが人気を集めました。
銀行窓販がスタートした後も、時流に乗ったファンドが次々新規設定され、それらのファンドを乗り換えていくという営業スタイルが続いていました。

分配金による資金流出の問題を考える
長澤 2016年頃から金融庁の方針のもと、「フィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営)」の強化が課題になりました。投資信託を取り巻く環境に変化は現れましたか。
清家 意識は変わったと思います。まず、運用実態に比べて高い分配金を出している毎月分配型ファンドを厳しく評価するようになりました。その結果、多くの毎月分配型ファンドは分配金の引き下げを行い、その影響で毎月分配型ファンドからは大量に資金が流出しました。
そして2014年にはNISA、2018年にはつみたてNISAがスタートして、「長期、分散、積立投資」が重視されるようになりました。とりわけ商品面では、つみたてNISAのスタートにより、低コストのインデックスファンドが人気化しました。
長澤 顧客本位の業務運営はかなり浸透したと思われますか。
清家 もともと高い販売手数料を取って、商品の乗り換えを促すような営業スタイルに問題がありました。ですから、乗り換え営業から残高営業・資産管理型営業への移行は、金融業界にとって大きな課題だと思います。
そのなかで、徐々にではありますが、販売手数料などフロー収入を中心とした営業スタイルから、信託報酬などストック収入を中心とした残高営業・資産管理型営業にスイッチする金融機関が増えてきたのも事実です。
ただ、資産管理型営業への移行はまだ道半ばといったところですね。たとえば証券会社や銀行の収益構造を見ると、販売手数料収入と信託報酬が50対50くらいです。したがって、信託報酬の収入だけで資産運用ビジネスを成立させようとしたら、投資信託やファンドラップの純資産残高を、2倍にしなければなりません。
では、それが実現可能なのかということですが、正直、金融機関の営業能力がかなり落ちてしまったので、なかなか純資産残高を倍増させるのは難しく、結果的に販売手数料に依存したビジネスになってしまいます。ここは大きな課題といえるでしょう。
長澤 純資産残高を2倍にしたいところですが、なかなか伸びないのも事実です。なぜ投資信託全体の純資産総額が増えないのでしょうか。
清家 公募投信の純資産総額は約160兆円あるのですが、そのうちETFが約60兆円、MRFが約15兆円、DC専用ファンドが約10兆円、ラップ専用ファンドが約10兆円あって、それらを除く、一般に売買されているファンドは、たったの65兆円しかありません。そして、その残高はこの10年間、ほとんど変わっていないのです。
そして、この10年間で日経平均株価が2.5倍、NYダウが3倍になったことを考えると、実質的には大幅な資金流出だったと考えられます。
なぜ資金流出が続いているのかというと、分配金の支払いによるものが大きいと見ています。実にこの10年間で、分配金による資金流出が30兆円もあるのです。この問題は真剣に考える必要があるでしょう。

OJTやロールプレイングの有効性
長澤 営業担当者のアドバイスは重要だとお考えですか。
清家 個人が1人で資産運用をするのは負担が大きいので、やはり金融の専門アドバイザーのサポートが必要だと考えています。
米国では、数千万円の資金を持っている人は大概、プロのアドバイザーに運用を任せています。欧州も同じです。
人間の行動は「リスクに見合ったリターンを求める」といった合理的なものではなく、「損失は一切せず、大きなリターンを得たい」というように非合理的ですから、個人が1人で運用しようとすると、間違った判断をしてしまいがちです。だからこそ、金融のプロがアドバイザーとして伴走する必要があるのです。
長澤 営業担当者の教育で必要なことは何でしょうか。
清家 机上論ではなく、OJTやロールプレイングがポイントになると考えています。たとえば証券会社では、販売チームのなかでのOJTを通じて営業ノウハウを学ぶ体制が確立されています。
一方、銀行ではチームとして十分に機能していないケースが散見されます。大事なことは、身近なところにいる優秀な先輩社員の一挙手一投足を見ながら、投資信託や金融の知識、お客様対応などをマスターすることだと思います。
投資信託の販売で実績を上げている金融機関は、営業員の教育でロールプレイングを重視しているケースが多く見られます。OJTやロールプレイングは実践的な学習です。それを行うことが、投資信託販売の存在感を再び高めるカギになるのではないでしょうか。
長澤 ありがとうございました。
(*)日本資産運用基盤の対談連載【金融ビジネス/これからの「顧客本位の業務運営」】の全てのバックナンバーはこちらからお読み頂けます。